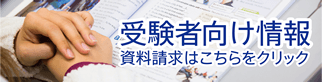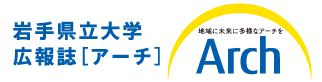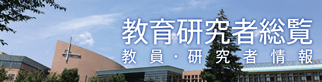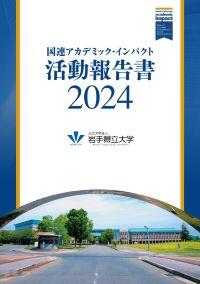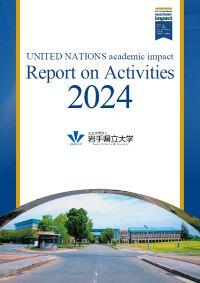国連アカデミック・インパクト活動報告書とは

国連アカデミック・インパクト(以下「UNAI」という。)の加盟大学は、UNAIの10の原則のうち、各年度に少なくとも1つの原則に係る活動を実施し、UNAI事務局に報告することとされています。
≪本学が参加する4原則≫
- 原則6 人々の国際市民としての意識を高める
- 原則8 貧困問題に取り組む
- 原則9 持続可能性を推進する
- 原則10 異文化間の対話や相互理解を促進し、不寛容を取り除く
2024年活動報告書の概要
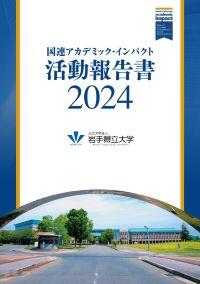
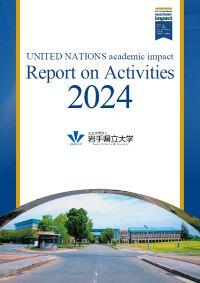
≪国連アカデミック・インパクト活動報告書2024の目次≫
■日本語版(Japanese Version)
「国連アカデミック・インパクト活動報告書2024」の概要・目次(PDF)
■英語版(English Version)
UNAI Report on Activities 2024 : Introdction(PDF)
1 健康課題の視点でSDGs解決策を考える
岩手県立大学看護学部 准教授 アンガホッファ司寿子、教授 細川舞
履修学生は、持続可能な開発目標ファクトシート(国連広報センター,2015)を参考に、グループごとにSDGs17の目標から関心を持った1つを選び、健康課題と関連した課題に着目し、国レベル、地域レベル、そして看護学を学ぶ大学生としての個人レベルで、解決策を考え発表している。発表後には質疑応答の意見交換により、さらに学びや考察を深めている。
この活動を通して、学生が国際的な視野で、医療保健や看護上の課題を考える機会を持ち、さらには看護学の領域を超え、学際的・政策的な視点で活躍する看護職を目指す意識が養われている。
■日本語版(Japanese Version)
「健康課題の視点でSDGs解決策を考える」活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
Considering SDG solutions from the perspective of health issues: Activity report(PDF)
2 岩手県内の自治体保健師と訪問看護師の連携を強化する取組
~岩手県の「にも包括」を共に学ぶ勉強会の開催~
岩手県立大学看護学部 地域看護学講座
教授 : 工藤朋子、准教授 : 後藤未央子、蘇武彩加、大久保牧子、講師 : 尾無徹、助教 : 髙岩奈津美、三井美波
岩手県立大学大学院看護学研究科 博士前期課程 菊池由紀
前岩手県立大学看護学部 地域看護学講座 教授 佐藤公子
本講座では、岩手県内の自治体保健師と訪問看護師の連携を強化していくための取組について検討を開始した。はじめに、両看護職の地域の共通課題である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築 (にも包括)」 に着目し、県本庁や保健所、岩手県訪問看護ステーション協議会など関係機関と情報交換を行い、県や圏域ごとの「にも包括」の動向、精神障がい者・家族への関わり、訪問看護ステーションの実情等を把握した。結果、両看護職の相互理解が深まることで、連携・協働が進むことが期待されたため、合同研修の企画に至った。岩手県の「にも包括」をより理解し、それぞれの役割を具体的に考えるきっかけとすることを目的に、勉強会を開催した。
■日本語版(Japanese Version)
「岩手県内の自治体保健師と訪問看護師の連携を強化する取組」活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
Efforts to enhance collaboration between municipal public health nurses and home-visiting nurses in Iwate Prefecture: Holding study sessions to learn together about Iwate Prefecture's comprehensive care system: Activity report(PDF)
3 地域と子どもをつなぐ学生の学び
― キッズボランティア「どろんこ隊☆」の実践報告 ―
岩手県立大学社会福祉学部 准教授 井上孝之
キッズボランティアサークル「どろんこ隊☆」は、2024 年に新たに2つの活動を立ち上げた。1つは、学習支援と居場所づくりを目的とする「どろんこ隊☆ミライ」による「タキ木の広場」、もう1つは、子ども食堂の企画・運営および支援を行う「どろんこ隊☆もぐもぐ食堂」である。
いずれも、地域の子どもたちの学びや生活を支えることを目的としたボランティア活動であり、学生が自らの問題意識に基づいて企画・実施を行っている。顧問は伴走的に支援しているが、活動の中心は学生にあり、主体的かつ自律的に展開されている。
■日本語版(Japanese Version)
「地域と子どもをつなぐ学生の学び」― キッズボランティア「どろんこ隊☆」の実践報告 ―活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
Students learning and bringing communities and children together: Practical report on the "Doronko Group" volunteer organization for children : Activity report(PDF)
4 地域の清掃活動の可視化を目的としたシステムの試作
岩手県立大学ソフトウェア情報学部 講師 富澤浩樹
岩手県環境生活部地域循環推進課
(株)Badass 代表取締役 田中裕也
本研究チームでは、ソフトウェア情報学部学生とともに、海岸・河川漂着物の実態調査のためのプラットフォームとなるシステムと、県民参加を促すためのデータ提供用アプリケーションの開発を段階的に行ってきた。具体的には、地域住民による組織的な清掃活動によって比較的環境が保たれていることに着目し、どの程度の量のゴミが拾われているかを把握することを目的としたプラットフォームシステムと多様なデータ提供用アプリケーションを試作することで、岩手県内に展開可能なシステムのあり方を模索している。
2024 年度は、これまでの研究に基づいて、地域の清掃活動の効果を可視化するためのプラットフォームと、清掃活動の経路情報共有を目的としたアプリケーションの試作を行った。これらは12月に東京ビックサイトで開催された「エコプロ2024」において展示された。
■日本語版(Japanese Version)
「地域の清掃活動の可視化を目的としたシステムの試作」活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
Development of a prototype system for visualizing community cleanup activities : Activity report(PDF)
5 残反の利活用による縫製企業とのデザインプロジェクトとその教育的効果
岩手県立大学盛岡短期大学部 准教授 佐藤恭子
(一社)北いわてアパレル産業振興会
㈱二戸ファッションセンター
岩手県県北広域振興局二戸地域振興センター
本プロジェクトは、盛岡短期大学部生活科学科生活デザイン専攻の学生2名が主体となり、「卒業研究」の一環として実施された。残反を活用した衣服デザインの提案・製作・評価を通じて、その活用可能性を検証することを目的とした。デザインの提案だけにとどまらず、実際の生産工程に関与することで、持続可能なファッションや長く着用できる衣服デザインとは何か、さらに現代に求められる衣服の在り方について考察することも、本プロジェクトの重要な狙いの一つである。
■日本語版(Japanese Version)
「残反の利活用による縫製企業とのデザインプロジェクトとその教育的効果」活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
A fashion design project conducted in collaboration with a sewing company to reuse remnants, and its educational benefits : Activity report(PDF)
6 副専攻・国際教養教育プログラムで開講している海外研修
岩手県立大学高等教育推進センター
国際教育研究部 教授 高橋英也、講師 江村健介
岩手県立大学には、学部・学科の専門 (主専攻) に加えて、それぞれの専門が活かされる「世界」を「地域」「国際」という視点から理解し、そこで生じる多様な課題に取り組む力を体系的かつ実践的に学ぶことができるプログラムとして、「地域創造教育プログラム」「国際教養教育プログラム」という2つの副専攻の課程がある。それぞれの課程の修了要件を満たすことで、「地域創造士」「国際教養士」の称号を得られる。国際教養教育プログラムは、グローバル化が進む世界を前に、異文化理解・多文化共生を基盤とした文化・社会を多面的理解に立脚し、自らと異なる文化的背景をもつ人々と協働し課題解決できる語学力を身につけ、主体的に行動できる実践力の育成を目指している。
■日本語版(Japanese Version)
「副専攻・国際教養教育プログラムで開講している海外研修」活動報告(PDF)
■英語版(English Version)
Overseas training through the International Humanities Education Program minor : Activity report(PDF)