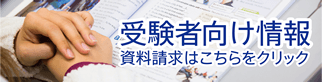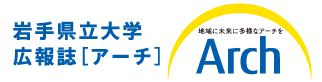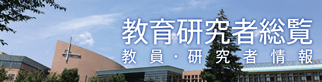北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクト推進センターについて
1 趣旨
岩手県立大学は、平成31年4月に岩手県と「北いわての地域課題の解決及び産業振興に向けた連携協力協定」を締結し、北いわての地域課題の解決及び産業振興を目的として、平成31年4月に当センターを設置しました。
2 活動紹介
(1)JST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」における取組
岩手県立大学では、令和3年度にJST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」(育成型(令和4年度から本格型))に県とともに参画し、気候変動と地域課題を「同時解決」する「ビヨンド・"ゼロカーボン"(※)」社会への転換を目指した取組を進めており、その一環として、北いわて地域における農林水産業の岩手型成長モデルの創出と展開を目指した取組を行っています。
※ビヨンド・ゼロカーボン:ゼロカーボンを達成したその先にある未来社会
COI-NEXT岩手サテライトの概要はこちら。
(2)北いわて(・三陸)地域活性化推進研究の実施
北いわて地域の活性化に資する調査・研究を支援するため、本学の教員等から研究課題を公募し、その研究を支援しています。
【これまでの研究成果(直近3ケ年)】 ※研究代表者は当時の職名を記載
|
研究課題名 |
研究成果 |
研究代表者 |
| R7 |
北いわて地域における県境を越える医療・介護連携の構築に関する諸問題の解明:久慈医療圏の医療DX推進と人的ネットワーク構築のための実証研究 |
研究中 |
看護学部
教授 岡田みずほ
|
| 施設職員が高齢者に効果的にケアを提供するためのICTを活用したサポートシステムの構築 |
研究中 |
看護学部
助教 鈴木睦 |
| インクルーシブeスポーツゲームによる地域交流プロジェクト |
研究中 |
ソフトウェア情報学部
講師 伊藤史人 |
| 他出子と関係人口のネットワーク化による集落支援モデル(ふるさと納Day)の実証普及に関する研究―西和賀町小繋沢地区への展開に向けて― |
研究中 |
総合政策学部
准教授 役重眞喜子
|
| R6 |
久慈医療圏の看護・介護職連携を推進するための地域医療情報連携ネットワーク(北三陸ネット)活用に向けた基礎的研究 |
詳細 |
看護学部 教授 岡田みずほ |
| 他出子と関係人口のネットワーク化による集落支援モデル(ふるさと納Day)の開発と運用に関する研究―岩手町豊岡地区をモデルとして― |
詳細 |
総合政策学部
准教授 役重眞喜子 |
| R5 |
社会福祉法人による「福祉でまちづくり」の実践とモデル構築 |
詳細 |
社会福祉学部 教授 宮城好郎 |
| 久慈地域の観光展示施設の魅力を高めるための知的ガイドシステムの構築と研究 |
詳細 |
ソフトウェア情報学部 教授 蔡大維 |
| 就労女性へのウイメンズ・ヘルスアクション啓発のためのピア・サポート共創アプローチモデル開発~北いわて地域特性に添った持続可能な実践の展開に向けて~ |
詳細 |
看護学部 准教授 谷地和加子 |
| 個人で継続可能な介護予防プログラムの構築 |
詳細 |
看護学部 講師 馬林幸枝 |
| 久慈地区における医療・介護連携の中で療養支援に必要な患者情報をつなぐための基盤研究 |
詳細 |
看護学部 教授 岡田みずほ |
| R4 |
北いわて・三陸地域の特性を考慮した夜間避難行動モデル構築に関する研究 |
作成中 |
総合政策学部
講師 杉安和也 |
北いわて・三陸地域の市町村における産前・産後ケアの実態
~地域特性に添った妊娠期から子育てまでの切れ目のない支援に向けた基礎的研究~ |
詳細 |
看護学部
教授 福島裕子 |
| 出産場所が消えた釜石市における、総合病院に勤務している助産師による切れ目のない妊娠・出産・子育て支援の現状と課題 |
詳細 |
看護学部
助手 山内侑里 |
| 医療的ケアの必要な子どもを養育する家族の仕事継続への支援 |
詳細 |
看護学部
准教授 原瑞恵 |
北いわての中小製造業企業におけるデザイン経営の実証研究
-㈱東光舎を実証事例とした参与観察型アプローチに基づく社会実装による検証- |
詳細 |
総合政策学部
准教授 近藤信一 |
| がん医療に携わるジェネラリスト看護師を支援するSNSを活用した「がん看護最新知識update」システムの構築 |
詳細 |
看護学部
准教授 細川舞 |
| 避難疲労による精神的健康度低下を低減する触覚デバイスの活用と評価 |
詳細 |
ソフトウェア情報学部
准教授 山邉茂之 |
| R3 |
ゲーミフィケーションを活用した特産物・観光・学習旅行促進システムの研究開発 |
詳細 |
ソフトウェア情報学部 教授 佐々木 淳 |
| ベテラン縫製職人の就業機会創出に関する調査研究 |
詳細 |
盛岡短期大学部 准教授 佐藤 恭子 |
| 北いわて・三陸地域の依存症問題支援ネットワークの調査及び自助グループ活性化策の検討 |
詳細 |
社会福祉学部 講師 泉 啓 |
| 田野畑産養殖わかめの高付加価値化に関する研究 |
詳細 |
総合政策学部 教授 山本 健 |
北いわての中小製造業企業におけるデザイン経営の実証研究
-参与観察型アプローチに基づく社会実装と検証- |
詳細 |
総合政策学部 講師 三好 純矢 |
| これからの「学校を核とした地域づくり」の研究 |
詳細 |
高等教育推進センター 准教授 渡部 芳栄 |