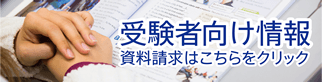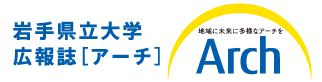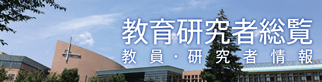|
R03北いわて・三陸地域活性化推進研究
「田野畑産養殖わかめの高付加価値化に関する研究」PDF
研究代表者:総合政策学部 山本健
共同研究者:田野畑村
|
<要旨>
田野畑村沿岸には入り組んだ湾がなく外洋の荒波で育った「田野畑わかめ」は、他の三陸産養殖わかめと比較しても葉自体が大きく肉厚であるという特長を有している。また養殖の過程でも、その種苗をすべて天然で採取しているという点で希少性も有している。岩手県の三陸沿岸は深い入り江のリアス式海岸が多く、こうした静水域で養殖されるわかめは柔らかさやつるんとしたのど越しの良さが人気を呼んでいる反面、外洋で育った天然種苗の田野畑わかめにはこれらにはないシャキシャキ、あるいはコリコリした食感と深い香りが特徴で、生産地市場では高く評価されている。本研究では田野畑村産養殖わかめの優位性がどのように評価され、どのように利用されているのかを解明するとともに、生産漁家がどのような問題に直面していて解決のために何が必要なのかを検討している。
1 研究の概要(背景・目的等)
田野畑村産の養殖わかめは生育環境においても、遺伝学的な素性においても有意性に恵まれ、大型で肉厚かつ高品質である点が高く評価され、岩手県内で最も高い価格で落札されている。日本のわかめ生産の大半は岩手・宮城の三陸海岸におけるもので、岩手県トップとは日本トップであり、日本トップということは世界で一番高い価格で取引されているということである。しかしながら、その生産に携わっている養殖漁家の収益水準は低く、そのことを反映して震災前には村内に44あった経営体は27にまで減少している。震災前は水揚げした港に隣接する作業場でボイルおよび塩蔵加工をして出荷していたが、復旧工事で住居や作業場を高台に移転させたことに伴い、岸壁からの運搬が困難となり、原藻のままトラックで引き取られるようになり付加価値の低下を招き、経営体数が著しく減少しているにもかかわらず、1経営体あたりの収入は震災前の水準を下回っている。
このように県内で最も高い浜値で落札されているにもかかわらず、その生産に携わっている養殖漁家は必ずしも経済的に恵まれていない現状に直面している。他にも過大な労働負荷の問題をはじめ、震災後10年余を経てなお改善を見ない諸問題を本研究で明らかにして、その解決策について検討を行うことを目的としている。
2 研究の内容(方法・経過等)
方法は、養殖漁家ならびにわかめ養殖の技術指導経験が豊かな岩手県水産技術センター元職員をはじめとする関係者に対するインタビュー調査、出版物・刊行物に対する文献調査によるもので、以下のような特性を持つことが明らかとなった。
日本近海に生息するワカメはナンブワカメと鳴門ワカメワカメに代表されるワカメに大きく分けられる。ナンブワカメは水深が深く潮流が速い海域に生息していて、茎が3メートルから5メートル程度と長く葉そのものが大きくて肉厚という特徴がある。一方のワカメは水深が浅く穏やかな海面域で養殖され、葉長は2メートル程度と短くて葉状部と胞子葉がつながっているのか特徴である。一般にナンブワカメは北方系、ワカメは南方系の典型として分けられることもあるが、三陸沿岸でもリアス式海岸の深い湾や入り江ではワカメが中心となったり、ナンブワカメでも東京湾の猿島で養殖されたりしている例もある。また田野畑村沿岸部では近年までトンネルや高架橋を伴う道路整備が進んでおらず、湾ごとに隔絶されてきたため、県内の他の地域のように外来種苗との交雑から守られ在来の天然種苗をもとに養殖が行われ続けている。このことにより、田野畑村産のワカメは他地域のそれと比べて香りが豊かであると言われている。肉厚で歯ごたえがあるという北方系の特徴では、宮古市の重茂半島や田老沖合で養殖されるワカメと変わらないが、種苗の違いがそれらに対する差別的優位となっていると思われる。
このようなワカメ自体の物理的特性と、田老の組合員数が約70、重茂が約120なのに対して田野畑は30にも満たない点を考慮すれば、恐らくその供給量の少なさを主な原因として高値での落札が続いているものと考えられる。ワカメは刈り取って海水から出してしまうと鮮度低下のスピードが速く、水揚から少しでも早くボイル作業をして添塩、芯抜きなどの作業を施した上で出荷するのが理想である。岩手県ではボイル、塩蔵、芯抜き、箱詰めまでの一連の作業を漁協が保有する加工施設で協業化している普代、田老、重茂、越喜来、広田湾などと、釜石や大槌で多く見られるそれぞれの漁家が自家加工施設ですべての工程をこなしているグループと、岸壁で先枯れ部分と元茎を切除して束ねただけで原藻のまま加工施設を保有する大規模な企業等に向けて生出荷するグループとの3つに大別することができる。
養殖ワカメの生産過程の中で最も負荷が大きいのが、海上における刈取り作業と湯通し塩蔵作業である。刈取り作業は1人ないし2人が乗り組む船外機付きの小型船舶で行われ、酷寒の2月から4月の深夜1時から朝5時ごろまでにかけて行われる。
湯通し塩蔵作業の過程は下表の通り。
|
原藻
|
良質の原藻を採取後なるべく早く処理する。概ね5時間~7時間で湯通し作業に入らなければ変色など品質低下が起こる。
|
|
湯通し
|
85℃~90℃に沸かした海水に均一に熱が伝わるように十分に撹拌をしながら湯通しする。
|
|
冷却
|
海水をかけ流しにして素早く冷えるように十分に撹拌する。
|
|
水切り
|
冷却したワカメに重しをかけて水切りをする。
|
|
塩もみ
|
原藻の40%量の塩を加えて、ムラがないように十分に塩もみをする。
|
|
塩漬け
|
塩もみしたワカメを容器に移し一昼夜塩漬けする。
|
|
芯抜き
|
元葉、芯、葉体に分離する。
|
|
脱水
|
適度の水分になるまで加圧して脱水を行う。
|
|
製品
|
劣化部位を切除して、仕分け・等級選別を行う。製品は-10℃~-15℃で保管。
|
ワカメの塩蔵加工(長谷川・鈴木2005より)
田野畑村には湯通し塩蔵作業を協同で行う加工施設がないため、これまでは個々の漁家が自家加工施設で一連の作業を行ってきたが、折からの人手不足と震災後の高台移転によって原藻の生出荷を余儀なくされる例が急増した。田野畑産ワカメの大口需要家は大規模な加工施設を持つ宮城県の水産会社で、岩手県北部から200km以上離れた石巻市や多賀城市の工場までトラックで輸送してから湯通し塩蔵作業に入るため、鮮度維持の観点からも田野畑における競りの終了・出荷時間が午前4時に設定されている。先に刈取り作業は深夜1時から朝5時頃までと述べたが、田野畑村では外洋域にまで出なければならないことも加わり前夜8時に出港して作業に当たらなければ間に合わず、このことも漁家の負担を増加させる要因となっている。
3 研究の成果
田野畑村産ワカメの浜値は1kgあたり1,700円前後であるが、湯通し塩蔵加工されて流通する価格は5,000円前後で、消費者向けに100g程度に小分けして袋詰めされた商品は10,000円程度になる例もある。鳴門産だと3,000円程度でも購入可能なことからも市場の評価は十分に高いと言える。
近年、国内産原料へのニーズが高まっている現状に加え、国内流通量の圧倒多数を占めている中国産ワカメの価格上昇もあって、おそらく需要サイドではさらなる供給を望んでいるに違いない。しかしながら、漁家の所得が増えず労働力の確保もままならない現状を考えると、まず村内に湯通し塩蔵加工施設を設置することが需要に応える上で急務である。養殖に携わる漁家の高齢化が進み、労働力の低下は避けられず、現在の過酷な労働負荷の軽減は不可欠である。漁協直営の工場の建設が難しいのであれば、村が設置して漁業関係者を管理者として運営するという方法もあるだろう。協業化によって生産性を向上させられれば、原藻の漁家からの買取価格も引き上げられるに違いない。また工場における労働力については、他の地域でも見られるように、普段は定置網漁などに従事している人々を湯通し塩蔵加工の繁忙期に振り向けることができれば、現状の生産量をさらに増やせる可能性も生まれるだろう。
4 今後の具体的な展開
本研究は関係者に対する聞取り調査を活動の中心にする事例研究であるが、研究期間を通じて新型コロナウイルスの感染状況が深刻で、とりわけ県外に所在する大手水産加工会社への訪問調査ができない状態が続いている。県内の関係者との間でも計画していた頻度を大幅に下回る回数しか調査を行うことができなかった。
引き続き、①ワカメ価格の決定要因の明確化、②共同作業施設整備のフィージビリティスタディ、③6次産業化体制の構築と整備に向けた提言の3点についての調査研究活動を行っていく。一連の活動を通じて①ワカメ養殖漁家の所得増加、②過酷な労働環境課の解放、③ワカメを中心とした水産物の高付加価値化の推進、④地域資源の有効活用、⑤担い手の確保と育成に貢献を果たすことができればと思っている。