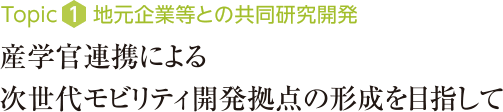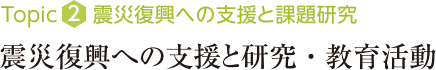- 地域に貢献する、開かれた大学を目指して
- 研究活動、および研究成果の還元による地域貢献の取組み
- i-MOS 研究課題
- Topic1:地元企業等と共同研究開発 産学官連携による次世代モビリティ開発拠点の形成を目指して
- 地域政策研究センター地域協働研究研究課題
- Topic2:震災復興への支援と課題研究 震災復興への支援と研究・教育活動
 岩手県立大学は「地域の活力創出に貢献する大学」を実現するため、地域連携本部を中心に産学公連携やシンクタンク機能の強化、県民への学習機会等の提供に取り組んでいます。
岩手県立大学は「地域の活力創出に貢献する大学」を実現するため、地域連携本部を中心に産学公連携やシンクタンク機能の強化、県民への学習機会等の提供に取り組んでいます。
平成24年度はi-MOSのもと産学共同研究や高度技術者の育成を推進するため、文部科学省採択の「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点」事業を活用し、自動車産業等ものづくり産業の振興に向けた産学共同研究を推進。高度技術者養成講習会ほか講習会・勉強会を開催し人材育成にも取り組みました(関連講座など受講者計277名)。
このほか地域の多様な生涯学習ニーズを踏まえ、岩手県立大学公開講座(滝沢キャンパス)や地区講座を開催。講座開催について広く周知活動を行うとともに、講演内容を収めた報告書を作成し配布しました。なお、平成24年度の地区講座では、震災復興をテーマに盛岡のほか宮古、釜石でも開催し、研究成果の公表やパネルディスカッションを行いました。
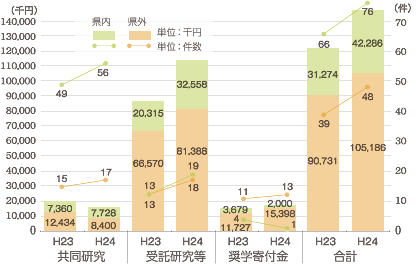 平成24年度はこれまでの外部資金の獲得に向けた取組みを進めてきた成果が見られ、外部資金研究件数・資金とも増加となりました。共同研究は前年度の64件(19,794千円)から平成24年度は73件(16,128千円)。受託研究等は前年度の26件(86,885千円)から、平成24年度は37件(113,946千円)となっています。
平成24年度はこれまでの外部資金の獲得に向けた取組みを進めてきた成果が見られ、外部資金研究件数・資金とも増加となりました。共同研究は前年度の64件(19,794千円)から平成24年度は73件(16,128千円)。受託研究等は前年度の26件(86,885千円)から、平成24年度は37件(113,946千円)となっています。
平成23年度に創設された「若手ステップアップ研究費」についても採択の適正化を図りながら運用を進め、平成24年度は19人に交付が決定。文部科学省採択の「いわて環境と人にやさしい次世代モビリティ開発拠点」事業(平成24〜28年度:交付決定額約5千万円)を活用した産学共同研究や技術者の育成など、地域の活力創出に貢献する多様な取組みを推進しています。
また、研究成果を県民に還元するため滝沢キャンパスや盛岡駅西口のアイーナキャンパスのほか、平成24年度には宮古や釜石など沿岸地域での開催をあわせた37の公開講座を実施、2,469人が参加しました。
|
|
いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(通称i-MOS)はソフトウェアとハードウェアの技術を基盤とするものづくり産業の集積を目指して、平成23年4月1日に設置されました。これまで学内研究費により33件の企業等との共同研究が行われているほか、A-STEPなどの外部資金を活用した研究や企業単独での製品開発の為の設備機器の利用も行われています。
平成25年度いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(i-MOS)の研究課題は以下の9件に決定しました。
| No. | 研究代表者 | 研究テーマ | 学部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 義孝 | Radio on Demand 機能により通信起動制御可能とする車載型全方位映像転送システムの実用化研究 | ソフトウェア情報学部 |
| 2 | 猪股 俊光 | 車載ソフトウェアの品質向上のためのソースコードの見える化の実現法 | ソフトウェア情報学部 |
| 3 | 新井 義和 | 前方環境の視認性向上のための対車両映像投影システム | ソフトウェア情報学部 |
| 4 | ゴウタム チャクラボルティ | RSU2V と V2V 通信に基づく避難車両への避難場所および避難経路情報の効率的な配信方式の提案 | ソフトウェア情報学部 |
| 5 | プリマ オキ ディッキ | 運転者の視線・頭部の姿勢・走行情報を利用した安全運転支援システムの実用化 | ソフトウェア情報学部 |
| 6 | 土井 章男 | 骨切り術のための3次元ベース術前計画支援システムの研究開発 | ソフトウェア情報学部 |
| 7 | 齊藤 義仰 | 人にやさしい車社会を実現するための感情共有技術の研究 | ソフトウェア情報学部 |
| 8 | 澤本 潤 | スマートフォン搭載加速度センサを使用した簡易地震計システムの提案 | ソフトウェア情報学部 |
| 9 | 藤田 ハミド | メンタルクローニングを用いた高齢化社会における交通事故防止システムの構築 | ソフトウェア情報学部 |

次世代モビリティの研究開発についての研究発表の様子
(平成25年9月、岩手県立大学研究成果発表会にて)
平成24年度に採択された「地域イノベーション戦略プログラム」(文部科学省事業)により、岩手県立大学及び県内の産学官と金融機関が連携し、将来を見据えた自動車産業の持続的なイノベーションを実現する地域を目指した取り組みを始めています。
岩手県立大学では、本学が有するポテンシャルを最大限に活かすため、次の取り組みを進めています。
県外から研究者を招へいし、次世代モビリティに関する研究開発を行うとともに、学内教員との協働による技術開発にも取り組んでいます。
また、コーディネーター等の配置により、次世代モビリティの新たな技術開発をサポート・加速させる体制を整備し、研究開発成果の地場企業への展開などを進めています。
さらには、「ものづくり」と「ソフトウェア」の両面の知識を有する技術者を体系的に育成するために、技術者・学生を対象とした高度技術者養成事業を実施し、人材育成にも取り組んでいます。
本学では、本事業への取組みを始めとして、産業振興による復興支援にも積極的に取り組んでいます。
「実学・実践重視の教育・研究」を基本的方向のひとつとする岩手県立大学では、県民のシンクタンク機能のさらなる充実強化をはかるために、地域政策研究センターを設置しています。「地域目線」で県民が抱える課題・ニーズに向き合い、多様な専門分野の研究者らが、自治体やNPO、企業との協働により、地域課題等を解決するための研究を行っています。
●地域提案型(前期)
多様な専門分野の研究者を擁する岩手県立大学に対して、県内の地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)が抱える課題を地域課題としてご提案いただき、そのあとの岩手県立大学の研究者とのマッチングを経て、共同研究として実施するものです。本研究を通じて得られた成果を活かし、提案者自らが課題解決に向けた具体的な取組みや活動につなげていただくことを目的とし、より地域に直結した取組み(調査・研究)が期待されます。平成25年度の前期は13件が採択されました。
| No. | 研究フィールド | 共同研究者 (提案者団体名) |
研究代表者 | 研究課題名 (研究計画策定後の課題名) |
所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久慈市 | 岩手県県北広域振興局 | 辻 盛生 | 森・川・海の一体的な取組みによる久慈湾の水質改善に向けた原因分析 | 総合政策学部 |
| 2 | 盛岡市 | 第一商事株式会社 | 宮城 好郎 | 民間介護事業者による地域密着型サービスのあり方に関する基礎研究 | 社会福祉学部 |
| 3 | 盛岡市 | 盛岡赤十字病院 | 山内 一史 | 電子カルテ導入前後の職員の業務量の比較と効果的な人員配置の検討(導入後) | 看護学部 |
| 4 | 大槌町、 陸前高田市、 宮古市 |
いわて デジタルエンジニア 育成センター |
土井 章男 | 東日本大震災における3次元復興計画の普及化による復興支援-3D復興計画モデルによる復興支援- | ソフトウェア 情報学部 |
| 5 | 宮古市、山田町、 大槌町、釜石市、 大船渡市、 陸前高田市 |
社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 |
都築 光一 | 災害派遣福祉チーム設置に関する研究について | 社会福祉学部 |
| 6 | 盛岡市 | 文化地層研究会 | 倉原 宗孝 | 盛岡の生活・空間資源(特に盛岡城跡周辺)の文化地層的な読解と活用法、及びその実践活動を通じたまちづくりと参加・協働の意識・体制づくり | 総合政策学部 |
| 7 | 久慈市、洋野町、 野田村、普代村 |
岩手県県北広域振興局 | 吉野 英岐 | 伝統野菜等の活用による6次産業化の展開 | 総合政策学部 |
| 8 | 雫石町 | 雫石町議会 | 齋藤 俊明 | 実効性のある議会改革について | 総合政策学部 |
| 9 | 滝沢村 | 滝沢村 経済産業部農林課 |
高木 正則 | 農作物の成長過程と農作業観察支援システムのグリーン・ツーリズムへの応用 | ソフトウェア 情報学部 |
| 10 | 久慈市、野田村、 宮古市、山田町、 大槌町、釜石市、 大船渡市、 陸前高田市 |
岩手県保健福祉部 | 狩野 徹 | 被災地の復興まちづくりにおけるユニバーサルデザインの実践について | 社会福祉学部 |
| 11 | 宮古市、山田町、 大槌町、釜石市、 盛岡市 |
岩手女性史を紡ぐ会 | 植田 眞弘 | 続・歴史に学ぶ「女性と復興」〜昭和三陸大津波と家族、共同体〜 | 宮古短期大学部 |
| 12 | 北上市 | 特定非営利活動法人 きたかみ観光ネクスト |
阿部 昭博 | みちのく民俗村のITを活用したユニバーサルデザインの検討 | ソフトウェア 情報学部 |
| 13 | 県内全域 | 公益社団法人 認知症の人と家族の会 岩手県支部 |
藤野 好美 | 若年性認知症本人の通所サービス利用の実態と課題について | 社会福祉学部 |
●教員提案型(前期)
岩手県立大学の教員(研究者)が地域団体等(県・市町村等の公共団体、地域団体、NPO、企業等)と行う共同研究を対象とし、研究者自らが提案する地域ニーズに対応した研究を行います。平成25年度からは、平成23〜24年度に実施した「震災復興研究」をこの「地域協働研究(教員提案型)」に統合し、東日本大震災からの復興を重点に置きながら取り組んでいるところです。
平成25年度の前期は「震災復興研究」8課題、「一般課題研究」7課題が採択されました。
| No. | 研究区分 | 研究分野 | 研究代表者 | 研究課題名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般課題 | 産業経済分野 | 阿部 昭博 | 地域観光クラウドのサービスモデルと観光振興に関する研究 | ソフトウェア 情報学部 |
| 2 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | 槫松 理樹 | 救急外来問診票からのトリアージ支援情報の獲得 | ソフトウェア 情報学部 |
| 3 | 震災復興 | 社会・生活基盤分野 | 藤村 史穂子 | 難病患者の災害時支援及び防災対策に関する研究 | 看護学部 |
| 4 | 震災復興 | 産業経済分野 | 青木 慎一郎 | 被災地従業員のメンタルヘルス支援による産業経済の再建 | 社会福祉学部 |
| 5 | 震災復興 | 暮らし分野 | 三浦 まゆみ | 勤務所属施設をもたないベテラン看護師の被災地住民への健康支援とそのプロセスに関する研究 | 看護学部 |
| 6 | 震災復興 | 社会・生活基盤分野 | 村山 優子 | 情報タイムカプセルを利用した持続可能な津波資料館の構築 | ソフトウェア 情報学部 |
| 7 | 震災復興 | 産業経済分野 | 渋谷 晃太郎 | 三陸復興国立公園及び東北海岸トレイルの漁船等を活用した多面的な利用推進に関する研究 | 総合政策学部 |
| 8 | 一般課題 | 暮らし分野 | 米本 清 | 非常時用車いす移乗ツールに関する試作・評価研究 | 社会福祉学部 |
| 9 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | プリマ・オキ・ ディッキ |
頭部および視線追尾システムを利用した肢体不自由者のための安価なコミュニケーション支援ツールの開発 | ソフトウェア 情報学部 |
| 10 | 一般課題 | 医療・看護・福祉 | 松川 久美子 | 脳卒中等生活習慣病予防に向けた保健介入プログラムの開発 | 看護学部 |
| 11 | 震災復興 | 社会・生活基盤分野 | 中谷 敬明 | 東日本大震災被災地域住民のこころの健康に関する研究-釜石市健康調査の分析による被災後の市民の精神的健康の実態把握- | 社会福祉学部 |
| 12 | 一般課題 | 地域社会・ コミュニティ・文化 |
細越 久美子 | 外国人散在地域における在住外国人の対人ネットワークと居場所感に関する研究 | 社会福祉学部 |
| 13 | 震災復興 | 産業経済分野 | 新田 義修 | 漁協の担い手(漁船漁業・養殖業)育成に関する研究 | 総合政策学部 |
| 14 | 一般課題 | 環境・資源・生活科学 | 千葉 啓子 | 北上産黒大豆「黒千石」の栄養機能性と加工食品への応用に関する研究 | 盛岡短期大学部 |
| 15 | 震災復興 | 社会・生活基盤分野 | 瀬川 典久 | HF帯を活用した被災者情報伝送システムの開発 | ソフトウェア 情報学部 |

サポートオフィス田老開所式(平成24年12月)

いわて学前期の現地講義の様子(平成24年6月、田野畑村にて)
岩手県立大学では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波による甚大な被害と、被害に伴う環境変化を受け、教職員・学生一丸となって震災対応・復興支援の取り組みを継続しています。
沿岸地区での復興支援活動を行う拠点として、本学は平成24年12月に宮古市田老総合事務所に「岩手県立大学復興サポートオフィス田老」、平成25年5月に釜石市平田の釜石・大槌産業育成センターに「岩手県立大学復興サポートオフィス釜石」を開設しました。大規模災害時にもつながる情報通信インフラの実験基地局として、衛星回線を使って情報伝達手段を確保するほか、教員の研究活動や現地での復興支援活動、学生のボランティア活動等の拠点等として活用していきます。
岩手県立大学の復興支援機関「災害復興支援センター」は平成23年度の設置以来、ボランティア保険への加入や経費の支援、必要な物資の貸与など、教職員と学生による自発的な復興支援活動に対する各種サポートを続けています。平成24年度は8回のボランティアバスの運行や、オハイオ大学と連携した復興支援活動などを行いました。
本学が主務校となって開講している県内5大学連携(いわて高等教育コンソーシアム)による共通授業「いわて学」は、平成24年度は「三陸・平泉から知るいわて」〜いわての復興を考える〜をテーマに実施。前期・後期各15回の授業を通して、岩手の魅力や復興について学びを深めました。
岩手県立大学は地域と連携しながら被災地への支援に取り組むとともに、復興教育にも力を入れて、未来につながる支援を進めていきます。