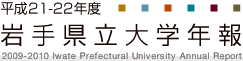平成21年度は、法人化第一期6年間の5年度目として、中期目標の達成状況に関する暫定的な評価を実施し、次期中期目標・中期計画に向けた大学運営の方向性を検討するとともに、中期目標の達成に向け下記の5項目に重点を置いて取組みました。
①教育力の一層の向上
入学から卒業まで一貫した教育システムの構築、幅広い知性を培う教育ならびに高度な専門性を養う教育のレベルアップ、単位の実質化と授業改善による教育効果の向上に取組みました。
●いわて5大学単位互換制度の充実
「戦略的大学連携支援事業」に基づいた新たな単位互換制度として、「地域人材育成講座(いわて学)」を本学が主務校となって検討し、平成22年度から開講することとしました。
|
||
|
●メディアセンターの学術機能の充実
学内で発行される研究論文等の収集を継続するとともに、収集した研究紀要はCiNii(国立情報学研究所論文情報ナビゲータ)により、平成22年10月末をめどに電子公開します。
図書館利用・資料・施設環境について、メディアセンター長と学生との意見交換会を実施したほか、学生から図書のリクエストを募集し、新着図書コーナーにて紹介する取組みを行いました。
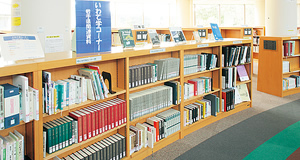 |
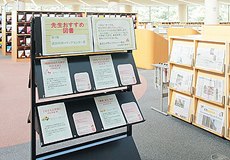 |
|
コーナーを設けて図書を紹介する取組み |
||
●ITの活用による教育支援
「教務・FD推進専門委員会」及び「学生支援専門委員会」において検討したうえで、「授業支援システム」及び「学生カルテシステム」を導入することとしました。
●がん看護専門看護師教育課程の認可
看護学研究科において「がん看護専門看護師教育課程」が認可され、3つの専門看護師教育課程を認定することができました。
②地域の課題に向き合った研究活動
課題を的確に把握する仕組みの構築、課題解決を具体的に推進する取組みの強化、提言・政策提案を行う体制の構築、研究成果の積極的な公表に取組みました。
●研究成果を地域活動に活かす取組み
「2009地域づくり・地域貢献活動セミナー&発表会」を開催し、地域づくり研究所では、学生ボランティアセンター、地域貢献研究会との共催により、「ワークショップを通じた地域づくりのデザイン」を実施しました。
地域づくり大学かねがさき校の成果発表会を開催し、公共政策研究所では総合政策研究科公共政策コースとともに、金ケ崎町が開催した「生涯教育の町宣言30周年記念大会」において、地域づくり大学での取組みを実践発表、ポスター展示を実施しました。
その他の取組みとして、「IPU地域づくりプラザ」のホームページ開設、盛岡市まちづくり研究所の成果報告会の共催、心身の健康づくりや福祉をテーマとした研究成果発表会や、県立大学生による学生活動発表会の開催、地域課題に対応した学術研究費の新規採択等を行いました。
 |
 |
|
学生による活動発表会(3月27日、いわて県民情報交流センター「アイーナ」にて) |
||
●学際的・横断的研究の仕組み検討
「地域専門職への遠隔教育システムの構築と実践的研究」の継続実施や、「がん患者の療養生活とQOL支援ならびにがん患者の充実・均てん化を目指した研究」の報告書を作成しました。
また、本学と岩手県、産業界で提案した地域産学官共同研究拠点事業「岩手県ものづくりソフトウェア融合テクノロジーセンター(仮称)」がJSTに採択され、平成23年度から本格実施される予定です。
●専門能力を高める学習の推進
西和賀地域での介護福祉士、社会福祉士の実習のほか、コミュニティ大学ワークショップ等の多様な学びの場を展開。また、学部内に「西和賀プロジェクト」を立ち上げ、大学祭において「西和賀映画会、シンポジウム」を開催しました。(社会福祉学部)
●大学・企業・地域の交流の推進
第5回いわて情報産業シンポジウム、首都圏企業就職フォーラム、仙台企業就職フォーラムの開催により、地域毎に企業と大学との活発な交流を実現できました。(ソフトウェア情報学部)
 |
 |
 |
||
いわて情報産業 |
首都圏企業就職 |
仙台企業就職 |
③県内高等学校との強固な関係の構築
中高生の学問への興味・関心を高める活動、県内高等学校との対話の促進、本学の教育に適合する学生の受入れ、高大連携事業の強化に取組みました。
●就学困難な学生への支援
平成21年度より授業料免除枠を拡大したほか、風水害による被害や家計支持者の死亡等の特別の事情による場合についても授業料免除を実施し、経済支援を行いました。
●入試問題、面接、評価方法の検討
面接担当者となる教員を対象に、講義および意見交換を行いました。「総合問題」を廃し、新たな配点方法を検討しており、AO入試についても今後見直しの方向で検討しています。(看護学部)
●推薦入学の入試制度の見直し
平成21年度入試の分析結果を平成22年度推薦入試の作題等に反映させました。また、今後の推薦入試制度の変更案をまとめるために、県内高校から意見聴取を行いました。(ソフトウェア情報学部)
●高等学校との連携の強化
土日も含めた学校見学の受け入れ対応や、「キャンパス見学会」、新たな取組みとして「学校説明会」を開催しました。また、高大連携の取組みの一つとして、「推薦入試合格者」の入学前教育を試行実施しました。(宮古短期大学部)
④不況期にあっても高い就職率の維持
キャリア形成意識の醸成、効率的・効果的な就職活動環境の提供、就職先の開拓と相互理解の促進、県内定着の推進に取組みました。
●実学実践の推進
カリキュラム改訂により、平成21年度から「地場産業・企業研究」を選択科目と位置づけ、展開科目とともに卒業要件としました。(総合政策学部)
●インターンシップへの支援
県内外の短期大学に、インターンシップ取組状況に関するアンケート調査を実施しました。インターンシップガイダンスにはほとんどの学生(76名)が参加し、うち46名がインターンシップに参加しました。(盛岡短期大学部)
●キャリア教育の導入
入門ゼミや基礎研究を通して、1年前期から進路についての状況や今後の取組みを認識させることを主眼としたキャリア教育を行いました。情報系の教育では、基礎研究において情報リテラシー教育を実施するとともに、パソコン検定協会「P検」を本学で実施する体制を整えました。(宮古短期大学部)
⑤教育研究活動推進力の抜本的な強化
大学運営業務の最適化、教育研究活動の実施体制の整備、教育研究活動を推進するモチベーションの向上に取組みました。
●研究倫理の向上
研究倫理審査委員会は原則として月一回開催し、一年間で35件の審査を行いました。
研究活動上の不正行為防止のため、平成21年3月に策定した不正防止計画に基づき、研究費の適正な執行のための手続きの明確化やその周知を行いました。
●次期中期目標・次期中期計画策定への取組み
中期目標期間の4年経過時における業務実績評価(暫定的な評価)を実施し、その結果をふまえ、次期中期目標・中期計画において、地域中核人材の育成と地域の活力創出を目指すための基本的な取組内容(骨子)をとりまとめました。