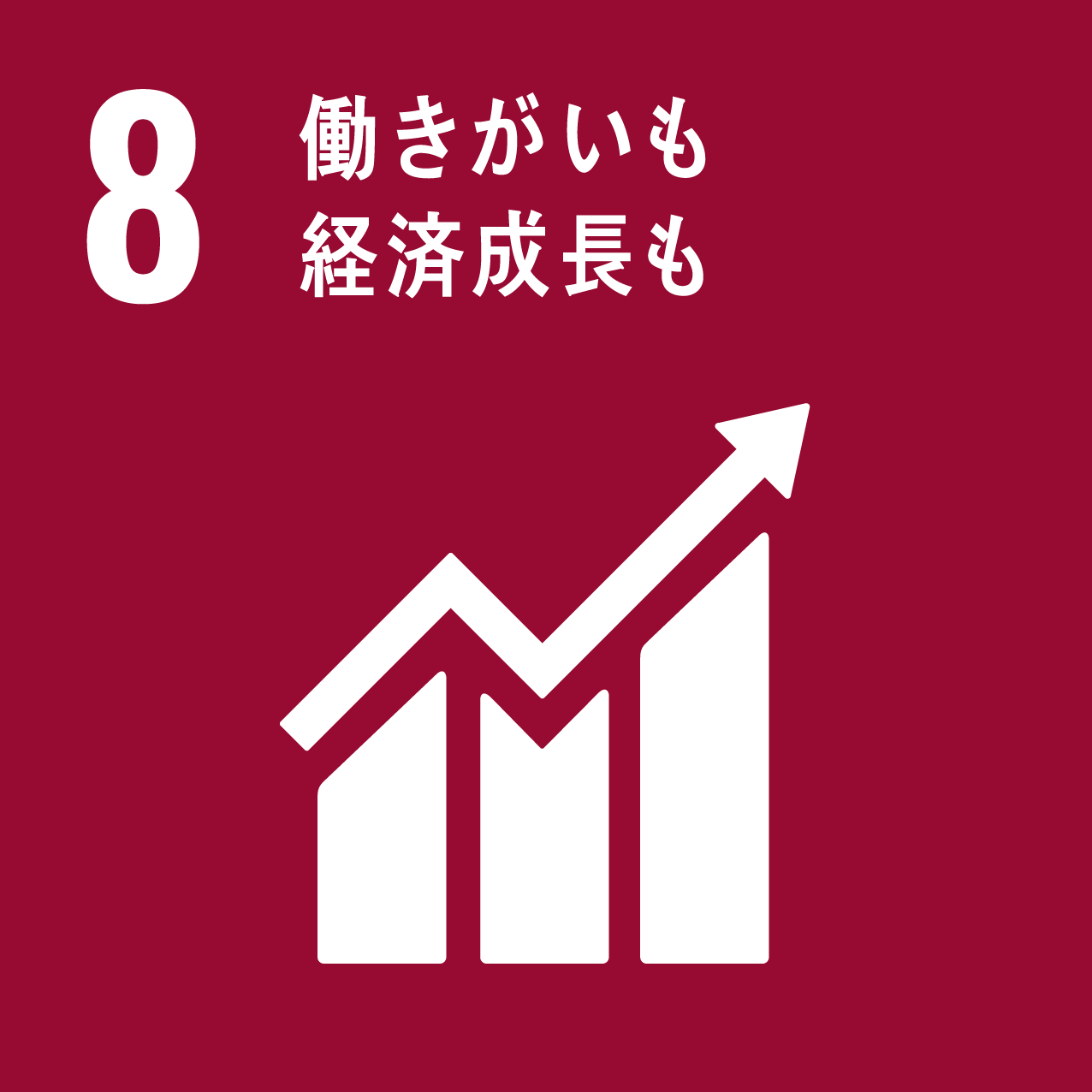令和3年度 地域協働研究(ステージⅡ)
歴史文化から耕す地方都市における住民主体・連携によるまちづくりの実践とモデル構築
| 研究番号 | 研究代表者 | 所属 | 職 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
R03-Ⅱ-02 |
総合政策学部 | 教授 | 倉原宗孝 | |
| 共同研究者(提案団体名) | 他の構成メンバー | 所属 | 職 | 氏名 |
| 紫波歴史研究会 | 総合政策学部 紫波歴史研究会 紫波歴史研究会 総合政策学部 |
講師 代表理事 会員 大学院生 |
三好純矢 佐藤観悦 大沼信忠 今野公顕 |
| 研究区分 | 一般課題 | 研究分野 | 地域マネジメント |
|---|
| SDGs |
|
|---|
| 研究フィールド | 紫波町 | 研究協力者 | 紫波町企画総務部企画課(予定)、紫波町産業部商工観光課(予定)、紫波町教育委員会生涯学習課(予定)、樋爪館懇話会・会長・高橋敬明、(株)よんりん舎・専務取締役・野村晋、史跡五郎沼愛護会・会長・ 箱崎勝之、南日詰活力センター・事務局・佐々木啓、赤沢まるごと博物館プロジェクト推進委員会・委員長・工藤睦夫、長岡歴史研究会・事務局長・七木田一善、佐比内山ひだの会・会長・山下研悦、彦部の歴史を深める会・会長・八重嶋勲、日詰商店会・会長・鈴木弘幸、紫波町芸能保存会・事務局長・高野修 |
|---|---|---|---|
|
① 解決を目指す課題(何を解決するのか) |
|||
| 研究成果報告書 | 岩手県立大学機関リポジトリへ | 研究概要(PDF) | ダウンロード | 研究概要(動画) | 県立大学公式Youtubeチャンネルへ |
|---|